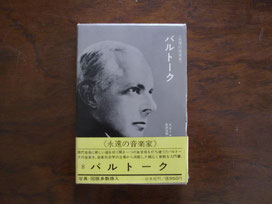
どの肖像を見てもバルトークという人物は虚弱に見える。
生後三ヶ月で打った天然痘の予防注射の発疹が5歳になるまで消えなかった。さらに肺炎のため、歩ったり、話したりできるまでに随分と時間がかかったというから先天的に丈夫でないのかもしれない。
ところが、どの肖像を見てもバルトークの眼光は矢のように鋭い。われわれが彼の音楽に感じる強烈な熱量と集中力はあの眼球から来ているように思えてならない。
強靭な意志を感じる。
2014年の最後の日に、私はバルトークの《管弦楽のための協奏曲》Sz.116を聴くことにした。この晩年の大作にもバルトークの眼光は鋭さを宿しているだろうか?
気になる記述がある。P.シトロンは1963年に出版され、日本でも訳されている彼のバルトーク論の中で、《管弦楽のための協奏曲》について、20世紀音楽に馴染のない大衆とって魅力的な作品であると断った上で次のように言い切っている。「それ自体としては傑作のひとつではない」。別のところで、西村朗だったと思うが、彼もバルトークの中でもこの作品は好きではないといった趣旨のことを書いていたと記憶している。なぜオケコンは玄人に評価されないのだろうか?
バルトークは1881年にトランシルヴァニア地方に生まれた。彼は愛国主義者であり、音楽についてはブラームスとかR.シュトラウス、リストを勉強したロマン主義者であった。そんなバルトークにとって1905年にピアノ・コンクールのために訪れたパリでの体験は大きな転機となった。そこで見たのものは、あらゆる自由と混沌が享受されている国際都市の狂騒である。複数の人種とそれに伴う言語が道端に飛び交っている。風俗は開放され、一方でアカデミズムも幅を利かせている。そして宗教的拘束もない。「パリ、神のいない神聖な都市」とバルトークは書いている。彼の中での既成概念は壊されたのである。1905年はバルトークがコダーイの民族音楽研究の存在を知った年でもある。その地点で、作曲家、民族音楽学者、ピアニストという音楽家バルトークのすべてが揃う。ここからアメリカに亡命する1940年までの間にバルトークは鋭さを宿していく。弦楽四重奏曲全6曲、《弦楽器と打楽器チェレスタのための音楽》Sz.106はその最高峰だといえるだろう。
では、亡命後の作品はどうだろう。未完の《ピアノ協奏曲第3番》Sz.119は、バルトークらしいリズムは健在であるが、それよりも金管を抑えた柔和なオーケストレーションや緊張感の少ない穏やかな曲調に美が感じられる。そして、例の《管弦楽のための協奏曲》であるが、こちらは1943年の作品。ここでも古典的な出で立ちが難解さを排除してくれる。第1曲の序奏付きのソナタ形式や終楽章のフーガは明晰で楽しみやすい。第4曲に出てくるショスタコーヴィチのパロディや〈一対の遊び〉でのユーモアのある旋律も親しみやすく感じる。その中で〈エレジー〉は不気味さを湛えているが、乾いたものではなく深い叙情があるので全体の核として馴染んでいる。
1939年以降、バルトークは常に厳しい状況にあった。母の死、第二次世界大戦の勃発に始まり、批評界の冷遇、健康面での悪化、貧困、1945年に白血病で死ぬまで、バルトークは虚弱な身体を何とか動かし、驚くほど頑固に意志を貫きながら何とか研究、作曲、演奏会をこなしていた。《管弦楽のための協奏曲》はその最中に誕生した大衆的で、力みなぎる大作である。古典的だがまったく擬古的ではなく、嘘っぽくない。ルネサンス音楽の対位法を熱心に研究していただけあってフーガにしても表現の質が高い。やはりこれもバルトークの偉業だと言えよう。感動的なくらいにポップであるということは、前衛に対するある種の反撃でもあるのだから、そういったところでもバルトークは鋭い洞察を持っていたと私は考えたい。
コメントをお書きください